お弁当は、朝作ってから実際に食べるまでに5~6時間くらいタイムラグがあります。
子どもにお弁当を持たせるとき、傷んでしまわないかすごく気になりますよね。
そこで今回は、現役(男子)高校生の母である筆者がふだんやっている「お弁当の食中毒対策」を紹介します。
息子にお弁当を作るようになって2年たちますが、以下の方法で夏場も切り抜けられたので、よかったら参考にしてください。
※なお執筆にあたっては、農林水産省: お弁当による食中毒を予防するために も参考にしました。
もくじ
お弁当作りで食中毒を防ぐ方法8つ
ここからは、食中毒を防ぐコツ8つを順番にご紹介します。
- ①清潔な弁当箱を使う
- ②ご飯はかために・味付けは濃いめに
- ③水分を極力入れない
- ④手で直接触らない
- ⑤冷たい食材を入れる
- ⑥できるだけ火を通す
- ⑦抗菌食材・抗菌グッズを活用
- ⑧完成後は、しばらく冷蔵庫へ
①:清潔な弁当箱を使う

弁当箱やカップは、洗剤でキレイに洗い、よく乾燥させたものを使いましょう。
(特にふたのパッキンに汚れがこびりつきやすいので、使用前は念入りにチェックすることをおすすめします!)
洗ってすぐにつめたい場合は、水分をよくふき取ってから作業してくださいね。
また盛り付けに使うさい箸なども、こまめに取り換えましょう。
②:ご飯はかために・味付けは濃いめに
お弁当用のご飯は、できるだけ「かため」に炊くようにしましょう。
水分量を少なくした方が、細菌が繁殖しにくいからです。
またかために炊くと、お米のデンプンがしっかりと糊化し、細菌がご飯粒の中に侵入しにくくなるという効果もあるのだとか。
ふだんよりも心持ちかため、を意識して炊いてくださいね。
またおかずやおにぎりの味付けは「濃いめ」を心がけましょう。
調味料に含まれる糖分・塩分・酸などは細菌の活動をおさえる働きがあります。
冷めると薄味に感じやすいので「ふだんより少し濃いかな?」くらいがちょうどいいと思います。
③:水分を極力入れない

お弁当に水分が混じると傷みやすくなります。できるだけ水気を切ってから入れましょう。
たとえば…、
- 夏場は生野菜(トマト・レタス・きゅうりなど)を避ける
- ミニトマトは洗ったあと、キッチンペーパーで水気をふき取る
- 冷凍食品も水分が出やすいので、同じくふき取る
パセリやレタス、見栄えが良くなるから入れたいけど夏はガマンガマン💦
またご飯におかずの水分が移るのも、危険です。
特に1段弁当の場合ご飯とおかずが密着しやすいので、仕切りやホイル・カップなどで区分けしましょう。
④:手で直接触らない

手の菌が付着するのを防ぐため、おにぎりやおかずには直接触れないようにしましょう。
おにぎりは、ラップごしに握った方が安心です。
…ただラップで握るときに気になるのが、「塩が均一に混ざらない問題」💦
私は最初、ラップに塩をパラパラ撒いてから握っていたのですが、それだとどうしても偏りが出る…。
ということで、
必要量のご飯をボウルにうつしてから、先に塩を混ぜる
に変えてみました。
そうしたら塩加減が均一なおにぎりになりましたよ!
よかったら試してみてくださいね。
⑤:冷たい食材を入れる
冷たい食材は「保冷剤」としても活躍してくれます。
特に便利なのが、冷凍食品。
冷凍食品の中には、レンジでチンしなくていいタイプもあります。
↓袋に「自然解凍OK」と書いてある、以下のような商品ですね。

自然解凍OKの商品は、20℃の環境・2~3時間でおいしく食べられるよう作られています。
夏場に冷凍食品を選ぶ際は、できるだけこの「自然解凍OK」商品を使うと便利です。
お弁当の定番おかずの1つ「イシイのミートボール」も、加熱調理ずみなので冷たいまま入れてOKなんですよ。知ってました?(私は途中まで全然気づかなくて、律義にレンチンしてました💦)
ご飯やおかずも、できるだけ冷ましてからつめましょう。
温かいと蒸気がこもり、傷みやすくなります。
⑥:できるだけ火を通す

おかずは、火を通してからつめるようにしましょう。
ハムやちくわなど、そのままで食べられる食材も、夏場は火を通した方が安心です。
また中心部までしっかりと火を通すのがポイント!
生焼けになっていないか、よくチェックしてからつめましょう。^
(もし生焼けになっていた場合は、耐熱容器に入れてラップをし、レンジで10秒~20秒ほど過熱すると、固まりやすいです)
作り置きのおかずをつめる場合も、再度加熱してからつめることをおすすめします。
⑦:抗菌食材・抗菌グッズを活用
こちらは定番対策ですね。夏場(気温20℃以上)のときは、抗菌グッズをお弁当に入れると安心です。
梅干し・ショウガ・酢の物・ネギ類といった❝抗菌食材❞を一緒に入れるのもいいですね。
またお弁当を持ち運ぶ際に「保冷バッグ」を使うようにすれば、持ち運び中の温度上昇を抑えられます。
⑧:完成後は、しばらく冷蔵庫へ
お弁当ができたら、カバンに入れる前に冷蔵庫でよく冷やしましょう。
できるだけ冷蔵庫の奥に入れると、均一に冷えやすくなります。
生ものや傷みやすいおかずが多い場合は、冷やす時間を長めにとってください。
時間が無いときは、冷凍庫で一気に冷やすのもおすすめです。ただし完全に凍ってしまわないよう、5分~10分ほどで取り出しましょう。
保冷効果の高い弁当箱もおすすめ!
いろいろと対策はありますが、「それでも夏は傷まないか心配…」という方も多いかもしれません。
そんなときは、保冷効果の高い金属製の弁当箱を使うのも1つの方法です。
また最近ではフタに保冷剤が内蔵されたものや、外気をシャットアウトしてくれるものなど…。
便利な機能が搭載されたものも販売されています。
安全性が気になる場合は、そういった弁当箱を用意してもいいですね。
万全の対策を取りつつ、安全にお弁当作りを楽しんでくださいね(*^^*)
↓先ほど紹介した弁当箱は、以下の記事で詳しく解説しています。興味のある方はチェックしてみてください。


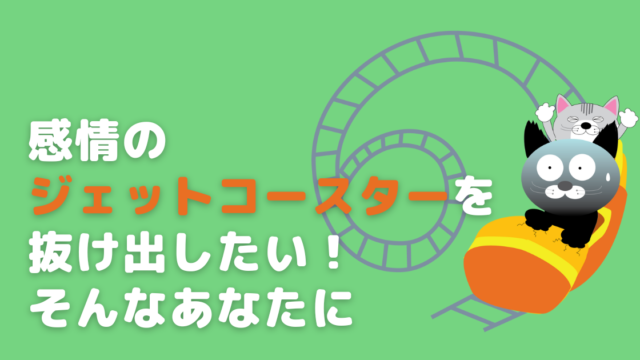










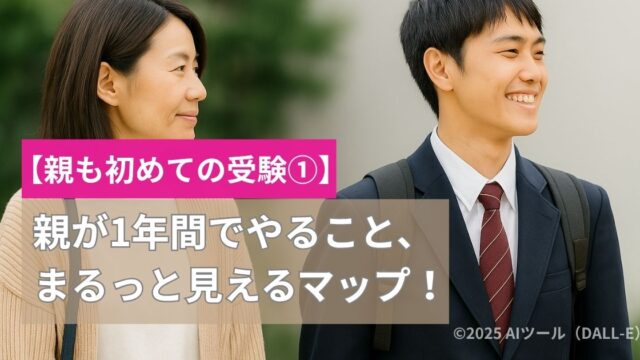

-3.jpg)



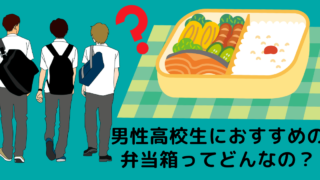

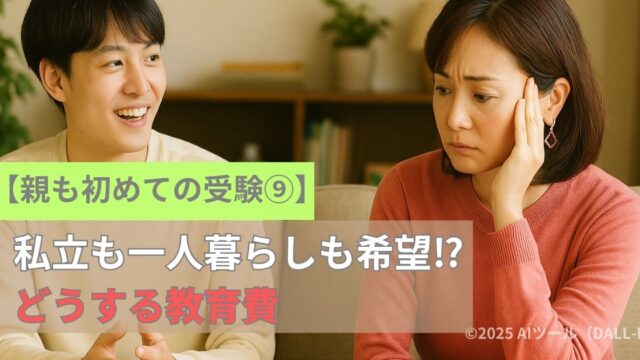
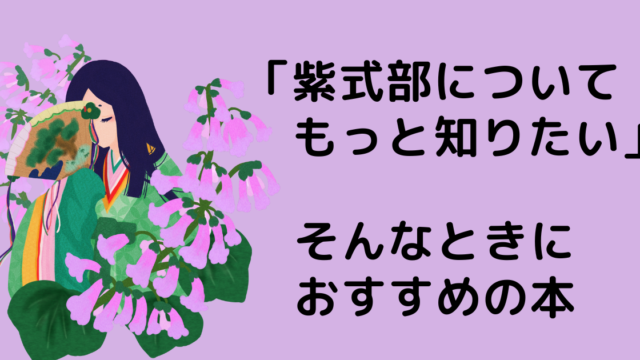


-150x150.jpg)