「学校がしんどい」に、親はどう向き合えばいい?

もくじ
不登校が増えているのはなぜ?
ここ数年、不登校の子どもたちが急増していますね。
でもよく考えてみると、今の時代はかつてより豊かで便利。
学校にもエアコンがあり、ネットや教材も充実しています。
昔よりずっと「快適な学習環境」のはずなのに、なぜ子どもたちは「学校がしんどい」と感じるのでしょう?
「甘えてるだけ」「根性が足りない」では、もう説明がつかないよね。
私は、今生まれてきている子どもたちと、親世代との間で、
大事にしたい「核」がズレてるような気がしています。
個人的な見解なので、参考程度にきいていただけると嬉しいです。
世代ごとに異なる「見えている世界」
以前の記事で、メンタルモデル という考え方について紹介しました。
メンタルモデルとは、「私はこういう存在だ」「世界はこういう場所だ」と、無意識のうちに信じ込んでいるフィルターのようなもの。
人は誰しも4つの“根源的な痛み”を無意識に抱えていて、それをベースに生き方や人間関係のスタイルができているのだそう。
その痛みから自分を守るために発動するのが「メンタルモデル」です。
メンタルモデルは4つに分類されます。
- 価値なし:「私には価値がない」
- 愛なし:「私は愛されない」
- ひとりぼっち:「私はしょせんひとりぼっちだ」
- 欠陥欠損:「私には何かが決定的に欠けている」
メンタルモデルは、4色の絵の具のようなもの。誰もが全部の色を持っているけど、人によってよく使う色は違うよ!
そして生まれ育った時代によって、強く表れやすいモデルは異なるといわれています。
昭和世代:「価値なしモデル」が色濃い
平成〜令和世代:「欠陥欠損モデル」の割合が多くなってきている
「価値なし」と「欠陥欠損」はどちらも「自分には足りない」という感覚があるんだけど、
以下のような違いがあるよ。
【価値なしモデル】
足りないと感じているのは、他人からの評価。だから外に目が向きやすく、他者の目に過剰に反応しがち。
【欠陥欠損モデル】
足りないと感じているのは、内面的な完成度。だから内に目が向きやすく、自分を厳しく見る傾向がある。
つまり、親と子では“見えている世界”が違っていて、自然ととる行動も変わってくるってことです。
このズレが、いろんな場面で食い違いを起こしているように思えます。
最近よく目にする、「価値なしモデル」全開の先生たち

最近、塾関係者が作る動画やブログをよく目にするんですが…。
そこで気になったのが、昭和世代の男性講師たちのこんな言葉でした。
「最近の子は、すぐ楽な方に逃げる」
「このままだと、日本の将来が不安です」
いわゆる“根性論”。
でもこれって、まさに
価値なしモデル(=がんばってなんぼ)を前提にした世界観です。
一方で、今の子どもたちの多くは、がんばる前から「自分は欠けている」と感じている「欠陥欠損モデル」の持ち主。
両者が持っている“前提”が違うからこそ、対話にならずすれ違いが起きているのかもしれません。
学校という仕組みがつくる「価値なしモデル」

そもそも学校教育は、「価値なしモデル」を量産するシステムです。
成績で評価され、比べられる
一律のルールに従い、個性はできるだけ抑える
「努力すれば報われる」が前提のシステム
たとえるならまるで、デコボコのあるジャガイモをきれいに削って丸く整え、規格品として出荷するようなもの。
もちろん、このモデルはかつての社会には合っていました。
高度経済成長期や一斉就職時代、みんなが同じ方向を向く必要があったからです。
でも、今の子どもたちは違います。
凸凹のままで生きたい。多様性を持ったまま、自分らしくありたい。
そういう願いを持っている「欠陥欠損モデル」の子の割合が、増えているのだと思います。
不登校の子どもたちは、その願いに素直に従っているだけかもしれません。
私はあっさり洗脳されてしまった昭和世代の1人なので、
彼らの敏感さや本質を見抜く力は、正直すごいなと感じています。
自分の中にある「葛藤の二重構造」
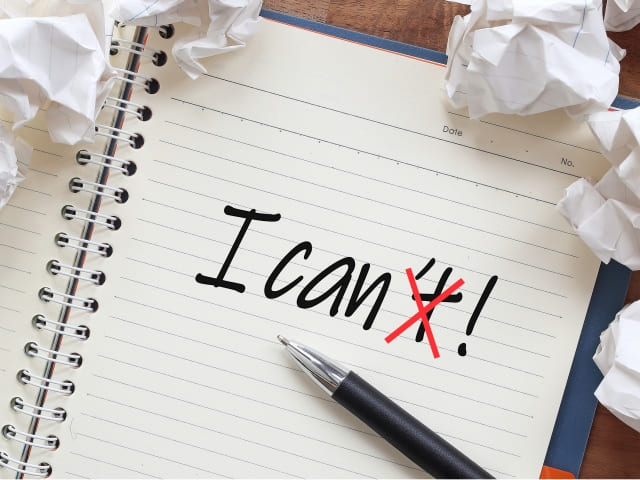
私は、「欠陥欠損モデル」の考えをわりと持っている方だと思います。
でも同時に、親や学校から教えられた「価値なしモデル」の影響も根強くあります。
がんばって成果を出せば、価値がある
でも本音では「がんばればがんばるほど、自分のポンコツぶりがむき出しになる気がして怖い」
がんばりたいのに、がんばるほど自己否定感が増していきます。
だったらいっそ、弱いままでいた方がラクかも…💦
まわりは「もっとやれ!」とハッパをかけてくるけど、力が出てきません。
最終的に、闘いのフィールドから降りてしまうこともしばしばです。
↓欠陥欠損モデルについては、こちらの方の解説がすごくわかりやすかったです!
わが家は夫が典型的な価値なしモデルなのですが、彼は、
自分であえて壁(目標)を設定して、それを克服することによって“強さ”を手に入れようとします。
その戦略が、欠陥欠損モデルの人と違うなあ…と感じています。(キーワードは「克服」?)
欠陥欠損の人は、戦いたくないんです。
ポンコツなままで、認められたいんですよ。
夫は自分の価値観をもとに、子どもをふるいたたせようと声かけしていますが、
空振り感がすごいです(^_^;)
似たようなことが、多くのご家庭で起きてるんじゃないかな…。
特に優秀な親ごさんほど「価値なしモデル」が強いので、よかれと思って自分のやり方を押しつけちゃってるかも。
子育てのヒント。「見えてる地図が違う」と知ること

不登校や学校への違和感に向き合うとき、つい親は「何とか元に戻してあげなきゃ」と焦ってしまいがちです。
でも、そこでまず大切なのは、
「親と子では見ている地図がまったく違う」という事実に気づくこと。
昭和的価値観のまま「とにかく努力」「逃げちゃダメ」は、子どもには届かない
子どもは“自分に合わない場所”を正直に感じ取り、そこから離れる力を持っている
もし子どもが「学校しんどい」と口にしたら、それは心のブレーキが正しく働いている証拠です。
そんなときは、こう伝えてあげられたらいいですね。
「合わないことは、おかしいことじゃないよ」
まとめ。「合わない=ダメじゃない」と伝えていこう

子どもが学校や集団生活をしんどく感じるのは、弱いからでも甘えているからでもなく、
親世代とは違うメンタルモデルを持っているのかもしれません。
そのことに気づくためにも、まずは親自身が
「自分はどんな前提で世の中を見ているのか(=メンタルモデル)」を知ることが、とても大きな手がかりになります。
そして「学校がつらい」「社会が合わない」と感じる子どもに対しては、
「それでもいいよ」「合わないのはおかしいことじゃないよ」と伝えてあげられたら、きっと心が軽くなるはずです。
社会のしくみに無理に子どもを合わせようとするのではなく、
「このままの自分で生きていていい」と思えるような場所や関係を、いっしょに探していく。
そんな関わり方こそ、今の子どもたちにとっての支えになるのではないでしょうか。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
何かの参考になれば幸いです(*^^*)
↓メンタルモデルについて解説された本です。
ちょっと分厚くて、内容も心理的にグッと踏み込んでくるので、最初はとっつきにくく感じるかもしれませんが…。
自分や子どもとの向き合い方にモヤモヤしている人には、すごく響く部分があると思います。
気になる方は、よかったら手に取ってみてくださいね。


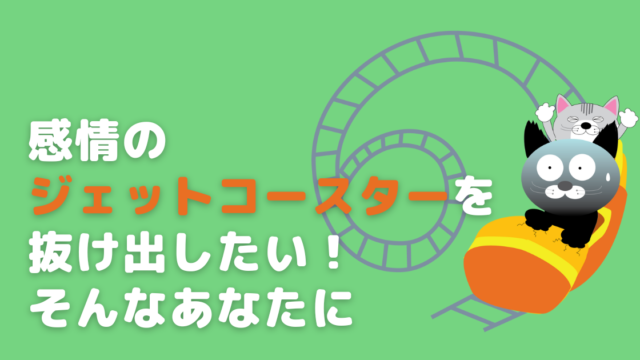










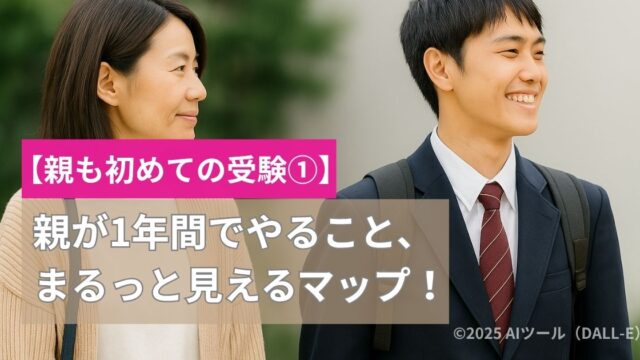

.jpg)




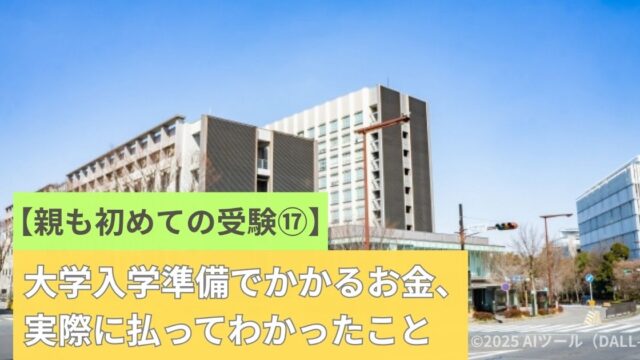

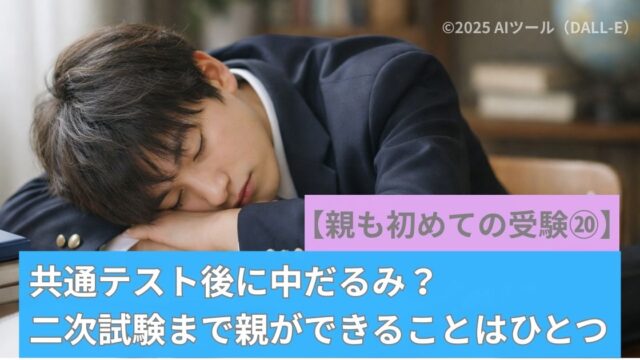


-150x150.jpg)